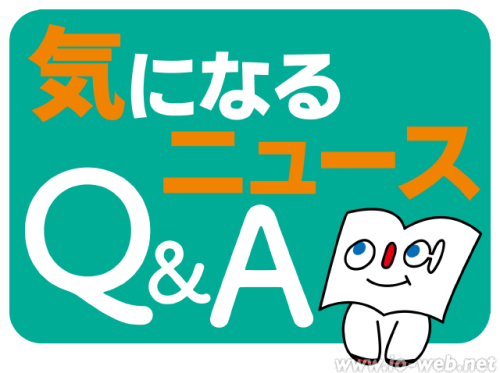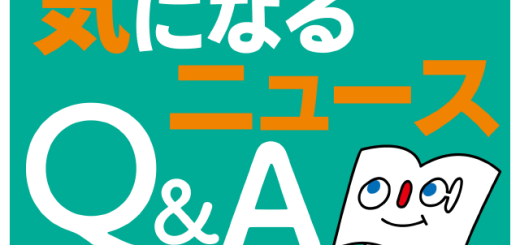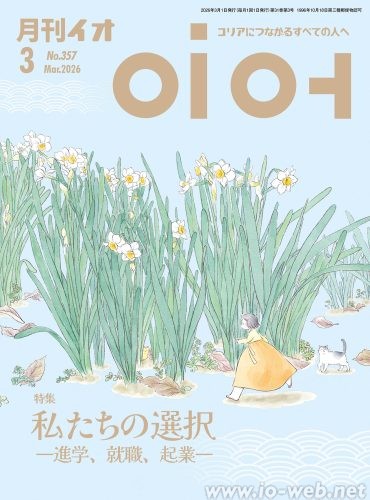vol.12 石破前首相の「戦後80年所感」
広告

「戦後80年所感」を発表する石破茂前首相(TOKYO MXのYouTube映像よりキャプチャ)
Q1 何が語られたのか
勝ち目のない戦争に、なぜ踏み切ったのか。その理由を問い直すことで、二度と未来を誤らないこと。そんな思いが所感に滲み出ています。戦前の日本で天皇は、旧日本陸海軍を動かす統帥権保持者でした。旧陸海軍は天皇に直属し、「皇軍」とさえ言われていました。それを口実にして、特に陸軍の高級幹部たちが統帥権を自分たちに都合よく解釈して、強大な権限を握り、果ては軍人内閣を創りました。この軍部の横暴を帝国議会も政党も止めることができなかった。財界もメディアも法曹界も学界も同じでした。そのことを指摘することで、文民統制の大切さを訴えようとしたのです。この文民統制が機能しないと、再び軍の暴走が始まるのではないか、と警鐘を鳴らしたと私は受け止めています。今日、自衛隊の強大化と日米同盟強化のなかで、文民統制の骨抜きが進んでいることも念頭にあったのでしょう。これが所感の最大のポイントです。
Q2 何が語られなかったのか
慎重さを欠いた部分と、抜け落ちた事柄があります。前者は、「平和と繁栄」が戦死者たちの上に築かれたとする常套句です。果たして、死者たちは国家のために戦地に赴いたのでしょうか。そうではなく、国家によって戦場へと動員されたのです。動員を敷いた国家、動員された日本軍によって甚大な被害に遭った人たちへの思いが不在です。歴史認識を表明する責務を持つ一国の首相としては、加害の責任を率直に語り、謝罪の気持ちを表すことを最優先すべきでした。
後者は、植民地支配の経緯や責任について、歴史を教訓とすると言いながら、一言も触れていないことです。日本敗戦直後、米ソ双方の思惑から、日本分断ではなく朝鮮半島分断となった経緯を知らない日本人は意外と多い。朝鮮半島の分断も日本の植民地支配の残滓であったのです。戦後も南北朝鮮は、分断が原因で争うことになっています。植民地支配の加害責任に触れてこそ、歴史を教訓とすることになるはずです。
Q3 所感の最後にある「歴史の教訓を踏まえる」とは
戦前の日本が歩んできた歴史を、未来において再び過ちを犯さないための鏡とすることです。その鏡が曇っていては、過去から教訓を引き出すことはできません。被害者たちは、「赦します。けれど決して忘れません」という言葉をよく口にします。
いつまでも憎み続けていても、被害者の生命は戻ってこないからです。だから加害者の過ちを赦すと言うのです。しかし、加害者はこの言葉に甘えてはなりません。
被害者は加害者を赦すことで、新たに共に生かし合う関係を紡ぎ出していくことを大切にします。でも、加害者は往々にして忘却し、被害者は懸命に記憶しようとします。加害者と被害者とが、忘却と記憶の闘いになってはなりません。
歴史の教訓を踏まえるとは、加害者と被害者との間で、和解と共立のゴールに辿り着くために努力することを意味します。加害者が被害者の言葉と行為に、どれだけ寄り添い、心から理解することができるのかが問われ続けているのです。