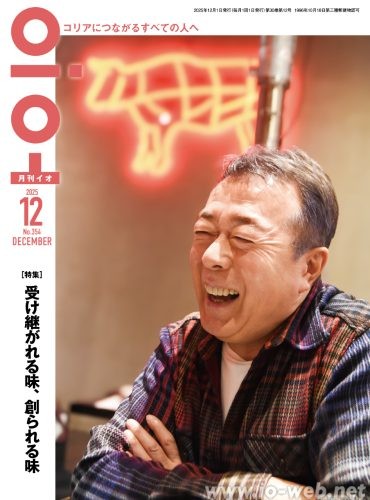イオ版 大阪・関西万博ガイド
広告

大阪・関西万博の大屋根リングの上
ルポ 万博を歩く
空虚な未来社会のデザイン
■ 国内・東アジアパビリオン
会場となる夢洲は、長らく大阪市のゴミ最終処分場として機能してきた人工島だ。廃棄物の上に土砂をかぶせる形で設けられた場内では、ガス爆発の原因となるメタンガスが開幕1週間前に検知されたほか、会場の地盤沈下やアクセスの悪さなどから大規模災害時の防災対策も不安視されている。そんな現状と、万博の目指すテーマが大きく乖離するのだが、実際の内容はどのようなものか―。

「誰もがあたり前に、健康に長く、安全・快適に暮らせる」未来都市を再現した巨大ジオラマ(飯田グループ×大阪公立大学共同出展館)
6月下旬のある日、万博会場を訪れた筆者は、日本の国内パビリオンと、その周辺地域となる東アジアの海外パビリオンを巡った。国内パビリオンは日本館にはじまり、地方自治体が運営するもの、企業や大学など民間が運営するものなど合わせて17のパビリオンで構成される。まず向かった先は、関西パビリオン。関西広域連合(2府6県4政令市で構成)が管轄する同パビリオンのテーマは「いのち輝く関西悠久の歴史と現在」だ。広報担当者の案内を受けながら場内へと進むと、高さ12メートルの吹き抜け空間が前方に広がった。「大関西広場」と呼ばれる各府県の情報をバナーで表示した柱を中心に、八方に京都、福井、滋賀、三重、和歌山、徳島、鳥取、兵庫の府県別ゾーンがある。
例えば三重県の場合、「出会う」「知る」「旅立つ」の3つのコンセプトで県内の豊かな自然や食、文化などを紹介しているのだが、気になったのは「悠久の歴史と現在」とうたうわりに歴史への言及、とりわけモノではない人の歴史についての言及が少ないことだ(ほかの府県も同様だった)。また言及されても伊勢神宮や熊野古道伊勢路など、同展示がいう「日本のこころの原点」の象徴とされるものたちの「歴史」がメインとなる。壁面スクリーンに投影された映像美、引き出しを開けると県内の名産品が出てくるといった視覚的な面白さもあって感心した一方で、「古くから、多様な人々が暮らしていた」というその中身や、その時代から続く現在の人びとの暮らしは、あまり見えない内容だった。

中国館に入ってすぐ、来場者らを迎える巨大円形の液晶ディスプレイは圧巻のスケールだ
…
独自の文化や歴史に触れて
■ 海外パビリオン
5月某日に万博会場を訪れた筆者は、海外パビリオンを中心に巡った。約160の国や地域、国際機関などから構成される同パビリオンは、「いのちをつなぐ」「いのちを救う」「いのちに力を与える」というテーマ別の3つのゾーンに分かれており、個性豊かな建造物が立ち並ぶ。

アルジェリア館のファザード
訪問当日は、事前調べで主に教育的な意義があった場所や、朝鮮とゆかりのある国々にフォーカスし、10ヵ所の単独パビリオン、そしてすべてのコモンズ館(複数の国や地域が共同で出展。A~Dまである)を観覧した。コモンズ館は並ばずに入れて、短時間で多くの国々を観ることができる。
コモンズ-Dを巡っていると、どこからかリズミカルな音が聞こえてきた。西アフリカのブルキナファソのブースだ。伝統打楽器ジャンベやバラフォンが置かれた同ブース。「実際に楽器に触れることで能動的な文化体験ができる。来訪者には私たちの文化を感じてほしい」とスタッフのドナルド・ノンギェルマさん(34)は語る。
1980年代に朝鮮と友好関係を築くも、親欧米政権が長らく続いた同国。一昨年に朝鮮と国交を回復した。フランスの旧植民地だった同国では、反仏感情の高まりから脱西側諸国の機運が高まっている。ノンギェルマさんの言葉の端々から感じる自国の抵抗精神に対する誇り。文化や歴史に触れることのできる、ひいき目なしでおすすめのブースだった。

ルクセンブルク館でネットの上に寝転びながら
…
私たちが観た大阪・関西万博
大阪や京都などの朝鮮学校の児童・生徒たちも万博を訪れている。世界各地の人々や物品、最先端の技術に触れることで主体的な学びや多文化への興味を促進させたい、というのが主な目的だ。会場を訪れた児童・生徒、教員たちに感想を聞いた。
京都朝鮮中高級学校 生徒、京都朝鮮初級学校 児童、京都朝鮮第2初級学校 引率教員、南大阪朝鮮初級学校 校長

京都朝鮮中高級学校 高級部3年生で記念撮影(写真はすべて学校提供)
「世界への扉」を開くきっかけに
南大阪朝鮮初級学校 校長

外国人スタッフとともに一枚
児童たちは、オーストラリア館では自然の雄大さを体感し、ドイツ館ではテクノロジーに驚き、パソナ館では未来の働き方に夢をふくらませた。「先生、すごい!」「こんな国に行ってみたい!」―そんな声があちこちから聞こえてきて、心があたたまった。特に印象的だったのは、フィリピン館で民族楽器を持ってフィリピンの方々と一緒にダンスをしたこと。躊躇なく踊りだす姿に、「さすがウリハッセン(朝鮮学校の児童)!」と誇らしさを感じた。…
寄稿・万博と人権抑圧、どう見る?
関西万博が開催されている大阪府内では一方で、朝鮮学校を助成金制度から除外するなど人権侵害的な状況が続く。万博計画はいかに推進されてきたのか、万博と人権抑圧をどう捉えるか、そして、万博にいかに可能性を見出すか。識者に寄稿いただいた。(編集部)
明戸隆浩●大阪公立大学大学院准教授

大阪・関西万博会場(大阪市此花区)前には参加国の国旗が掲揚されている(写真は西ゲート前)
大阪・関西万博の計画が最初に文書で示されたのは2014年8月、1回目の大阪都構想の住民投票に向けて、大阪維新の会が「大阪広域マニフェスト」を発表したときのことだった。発案者である橋下徹は08年に大阪府知事に当選した後、10年に大阪維新の会を結成、翌11年には大阪市長に転身し(大阪府知事には松井一郎が当選)、14年3月の出直し選挙で再選していた。大阪都構想は翌1年5月の住民投票で否決されるわけだが(20年には2回目の否決)、万博計画はIR(統合型リゾート)や大阪市立大学と大阪府立大学の統合などとともに、その後も推進され続けることになる。
その一方で大阪維新の会は、差別や人権に対して抑圧的な姿勢をとり続けてきたことでも知られる。たとえば大阪人権博物館(リバティおおさか)は、12年4月に橋下大阪市長と松井大阪府知事が揃って視察した後、展示内容が「子どもが夢や希望を抱けるようなものではない」ことなどを理由に補助金が打ち切られ、最終的に20年6月に休館に追い込まれた。また10年に国が高校無償化制度を開始するにあたって朝鮮学校への適用を留保した際には、これに呼応する形で橋下大阪府知事が府の補助金交付への「条件」を提示、10年度には一部補助金を交付したものの、11年度以降は大阪府・市ともにすべての朝鮮学校に補助金を支給しない不合理な状況が続いている。
…
以上が記事の抜粋です。全文は本誌2025年8月号をご覧ください。
定期購読はこちらから。
Amazonでは一冊からご注文いただけます。