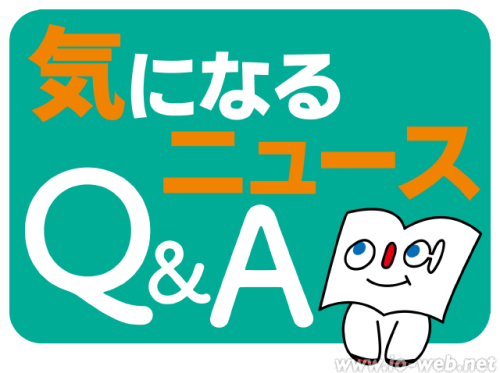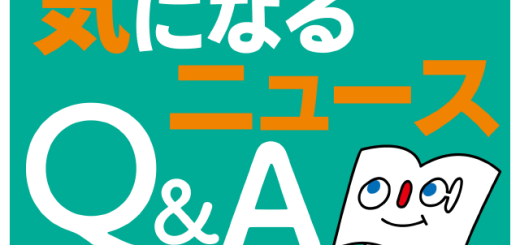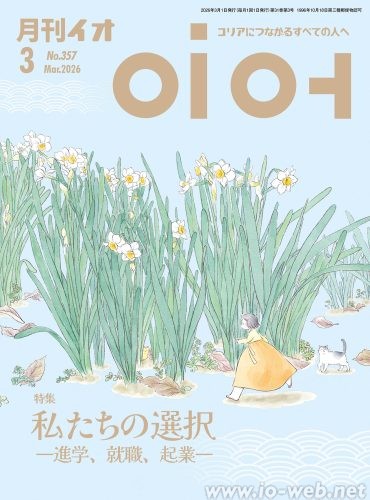vol.6 ネット上での誹謗中傷
広告

総務省(東京都千代田区)
Q1 何が決められたの?
総務省は、情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法、情プラ法)を施行した。インターネット上における誹謗中傷などによる人権侵害が深刻化していることが背景にある。
情プラ法では、事業者に対して、投稿内容で権利を侵害された人からの削除申請を受け付ける窓口の整備と公表、申請受理から7日以内に判断・申請者に通知することを義務付けた。また、削除基準の明示、投稿を削除した場合は発信者に通知することを求める。措置の実施状況の公表も求め、違反事業者には国が勧告・命令を出し、従わなければ最大1億円の罰金を科す。
対応を義務付ける事業者に、YouTube(Google)、Yahoo!知恵袋(LINEヤフー株式会社)、Instagram(Meta)、X(旧Twitter 、X社)、TikTok(TikTok社)などのサービスを提供する5社が指定されている(5月1日現在)。
今年3月には、情プラ法の施行に先立ち、削除の対象となり得る不適切な投稿を例示したガイドライン(総務省作成)が公表された。名誉棄損、プライバシーや著作権の侵害例のほか、闇バイトの広告などが含まれており、事業者に自主的な削除対応を促している。
Q2 誹謗中傷の事例、やまない原因は?
20年、テレビ番組に出演していた女子プロレスラーの木村花さん(当時22歳)がSNS上で多数の誹謗中傷を受けて自死した。事件を機に、誹謗中傷への問題意識が広がるも、その後もやむことはなく、昨年のパリ五輪開催期間中、トランスジェンダー選手などに対する誹謗中傷が散見された。今年には、兵庫県知事に関わる疑惑を調査していた元県議会議員が自死した。SNS上での誹謗中傷が一因とみられる。
高度情報社会において、閲覧数が収益に直結すること(アテンション・エコノミー)が過激な、あるいは虚偽の投稿が広がる一因との指摘がある。 20ネット上では、自身が好む情報ばかりが優先的に提示される「フィルターバブル」によって意見が先鋭化し、似た価値観の人々とだけ交流することで特定の意見や思想が増幅されて影響力を持つ「エコーチェンバー」により、誹謗中傷が「正しい行為」として共有されやすくなる。
誰もが情報を発信できる時代。SNS上で安易に不確かな情報を拡散しないなど、私たち一人ひとりの「情報リテラシー」の向上が求められている。
Q3 課題は?
総務省は、情プラ法を「『被害者救済』と発信者の『表現の自由』という重要な権利・利益のバランスに配慮しつつ」対処するための法整備だと主張している。
ただし、「表現の自由」の理念と現実の間には大きな隔たりがあることに留意する必要がある。日本社会では、「表現の自由の保障」が、在日コリアンをはじめマイノリティへのヘイトスピーチを正当化する口実などで多用されているからだ。
今回、削除の対象とされたのは、誹謗中傷など「他人の権利の侵害」と認められた投稿だが、不特定多数を対象とした「差別扇動」であるヘイトスピーチやフェイクが氾濫するデジタル空間を前に課題は山積している。昨年の能登半島地震の際には「朝鮮人が井戸に毒(を入れた)」などのデマが流れた。関東大震災時のような朝鮮人虐殺を繰り返してはならない。「差別されない権利」が侵害されているなかで、法の規制が及ばない偽・誤情報の対策についても議論を活発化していくことが求められる。
参考:
・特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律第 26 条に関するガイドライン(https://www.isplaw.jp/vc-files/isplaw/26G.pdf)
・情報流通プラットフォーム対処法の省令及びガイドラインに関する考え方(https://www.soumu.go.jp/main_content/000978031.pdf)
・情報流通プラットフォーム対処法第20条第1項に基づく大規模特定電気通信役務提供者の指定(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01ryutsu02_02000435.html)
・山口真一「人類総メディア時代の表現の自由」、『現代思想』2025年5月号特集「表現の自由」を考える