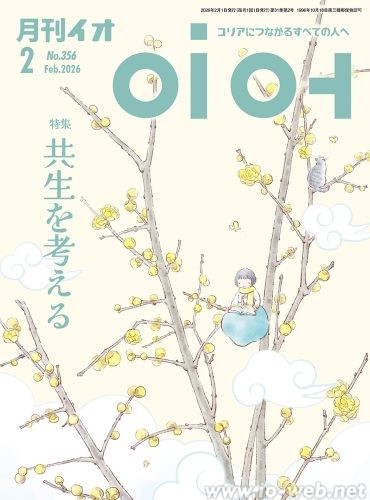新宿梁山泊第80回公演『恭しき娼婦』を観て
広告

先日、久しぶりに新宿梁山泊の舞台を観に行った。演劇のタイトルは『恭しき娼婦』。12月11日から18日まで下北沢のザ•スズナリで上演された同劇団の第80回公演だ。
『恭しき娼婦』はジャン=ポール・サルトルが1946年に発表した戯曲。アメリカを舞台に、無実の罪を着せられて逃走する黒人青年をかくまう娼婦リッジ―と、彼女に虚偽の証言をさせようと迫る街の権力者の息子フレッドを軸にした物語だ。
あらすじはこうだ。
ある日、娼婦リッジー(サヘル・ローズ)は黒人男性が地位の高い白人男性に射殺された事件に巻き込まれる。電車内でたまたま居合わせた黒人男性2人に白人男性がいいがかりをつけた上に、そのうちの一人を撃ち殺してしまったのだ。そこで生き残ったもう一人の黒人男性が助けを求めてリッジーのアパートを訪ねる。リッジーは判事に呼び出された場合は真実(黒人たちは何も悪いことをしていないのに撃たれた)を証言すると告げる。しかし、その街の権力者の息子フレッドが彼女に虚偽の証言をさせようと迫る。白人の言うことを聞いて虚偽の証言をするのか、黒人を救って正義を貫くのか。嘘をつけば守られる、真実を言えば傷つけられる。リッジ―が下す決断とは――。
印象深い場面は多々あったが、中でも、フレッドの父親である上院議員のキャラクターだ。虚偽の証言をすることをリッジ―に迫る警官たちに、無理強いしてはいけない、証言にサインするかどうかはリッジ―自身が決めるのだ、ともっともらしいことを言いながら、上院議員は弁舌巧みにリッジ―がサインするよう迫っていくのだ。そしてリッジ―は上院議員の巧みな言葉に乗せられて、ついには虚偽の証言書にサインしてしまう。
差別と、権力による沈黙の強要。それでも「嘘をつきたくない、本当のことを言いたい」と必死に抗うリッジー。しかし―。国家対黒人、あるいは国家対娼婦という、権力を持つ者と社会的弱者という圧倒的格差の中で自由を全うできない不条理。強者によって弱者の尊厳が奪われていく。80年近く前の作品だが、現代に生きる私たちも深く心を動かされる普遍的なテーマではないだろうか。
原作の終わり方はあっさりとしているが、今回の舞台では独自の演出が加えられている。世界へ痛烈な怒りを投げかけるごとく、客席に鋭い眼差しを向けてその場に立ち尽くすリッジ―。全身で感情を表現するサヘル・ローズの演技に引き込まれた。
サルトル作のこの戯曲は、社会の不条理により人間の尊厳がいかに奪われるのかを真正面から問うている。今回の上演では主演のサヘル・ローズと劇団の代表で演出家の金守珍が、「自分たちの物語」として同時代の人々に向けて発信したいという強い思いがあったという。
本作は金守珍が師と仰ぐ唐十郎の劇団「状況劇場」の旗揚げ作品でもある。新宿梁山泊ではこれまで2018年と22年の2度本作を上演。海外(ポーランド)でも公演を行った。初演では、舞台を現代の日本に、虐げられる黒人を在日朝鮮人に置き換えた。
20世紀に人類が克服を誓ったはずの戦争、民族差別は、なくなるどころか今なお激しく世界を覆っている。 2025年12月、内外情勢が混迷を深める中、本作の再再演を敢行したということ自体が劇団としてのストレートなメッセージなのだと感じた。
新宿梁山泊は来年秋に山口県の長生炭鉱水没事故を物語として現地でテント上演する予定だという。(相)