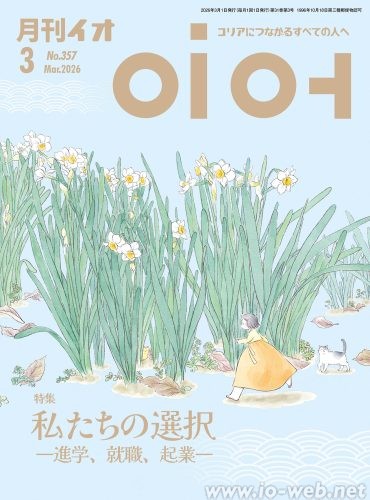〈人生羈旅 ②〉経験と余白が思考を深める
広告
「月刊イオ10月号が完成しました!」のブログ担当が回ってきて、1回分空いてしまったが、前回につづき夏旅の紀行文②を書き記したい。(①はこちら)
長野県野沢温泉村での2日目。①の冒頭で本旅の目的は、温泉、登山、読書、自分との対話、デジタルデトックス(、食い倒れ)だと綴ったが、この日は午前から山を登った。 標高1650mの毛無山の山腹に広がる上ノ平高原。ブナの原生林が特徴的だということで、早速リフトに搭乗し、ブナ林のあるところを目指した。だがしかし。この日の服装は、黒の半そでにせめてもの長ズボン。
標高1650mの毛無山の山腹に広がる上ノ平高原。ブナの原生林が特徴的だということで、早速リフトに搭乗し、ブナ林のあるところを目指した。だがしかし。この日の服装は、黒の半そでにせめてもの長ズボン。

軽い気持ちでブナ林コースに足を踏み入れたが、思ったより道が狭く木が生い茂っていたため、すぐに抜けた。その後は、アシナガバチに狙われて、久しぶりに全力疾走したため、酸欠気味に。疲労感でどっと足が重くなったので、早々に切り上げて下山した。
気を取り直し、この日は外湯(共同浴場)巡りをすることにした。野沢温泉村には13の外湯がある。地元の人が管理をしており、地元民のみならず外から来た人にも開けていて、無料で入浴できる(賽銭箱が置かれている)。最初は湯が熱すぎて入れないところもあったが、巡っているうちにいい湯加減のところを見つけ、体を休めた。たまにこの異邦人に話しかけてくれる人もいて、アットホームでいい雰囲気の場所であった。
ちなみに、いくつかの外湯のすぐ近くに置かれた木箱の中で温泉卵を作ることができる。生卵とネットはお土産屋などで買えるが、まさかの3玉で販売。ここでひとり旅の弊害が出たか…と思いつつ、購入。外湯前に群がっていた学生らしきグループを横目に卵をお湯に浸けた(1玉は旅館に置いていった)。少し虚しくなったが、気にしない気にしない。

出来上がった温泉卵に満足したところで、旅館に戻って本のページをめくった。
前夜から読み始めたのは、吉野源三郎著『きみたちはどう生きるか』(1937年初出版)。再読本だ。難解に解釈しがちなことを平易な言葉で説明する作中の「おじさん」に大人も学ぶことが多い。
「ある時、あるところで、君がある感動を受けたという、繰り返すことのない、ただ一度の経験の中に、その時だけにとどまらない意味のあることがわかって来る。それが、本当の君の思想というものだ」「常に自分の体験から出発して正直に考えてゆけ」(おじさん)
この言葉がすとんと落ちていく感覚があった。
忙しなく情報が入ってくる日々のなか、大事なものを忘れていたのではないか…。普段と異なる地へ赴いてさまざまなことを経験し、本を読み、考える。すると、本を横断して共通項を見出したりもする。
月刊イオの別冊本の組版を協議する際、何もないページ、「余白」を設けるかどうかの議論をした。その際に「考える余地」を設ける意味であった方がいいという意見が出たが、行間や余白のおかげで、別の本や雑誌などで読んだ言葉と言葉が繋がる。
旅に本を3冊持参したと前回のべたが、最後は、宮島未奈著『成瀬は天下を取りにいく』(2023年、新潮社)だ。よく意識される「普通」の人とは何か、さらに言えば、どう生きるのかを問うている。この爽快な主人公・成瀬あかりが魅力的だ。ちなみに、舞台は滋賀県大津市で、膳所の町がもっとも多く登場する。膳所駅は、滋賀朝鮮初級学校の最寄りだ。旅中に本作を読み切り、帰った後は、続編の『成瀬は信じた道をいく』もすぐに読んだ。
本を読み続けることで、本を読む体力がつく(『長い読書』)という島田潤一郎氏の指摘は正しい。(この次の日を含めて)3日で3冊読破。久しく高密度で読書をした後は、筋トレ後に筋肉が肥大するかのように読書熱が続いた。
〈人生羈旅〉最終回は、徐京植さんの『私のアメリカ人文紀行』に触発されて、丸木美術館(埼玉県)へ訪れた話をしたい。(哲)