web版万博ルポ・「世界」を間近に
広告

5月末、私は大阪・関西万博を訪れた。これから綴るのは、ごく私的な訪問記であり、参考になるかわからないが、記録として残しておく。
イオ編集部の記者は、2025年日本国際覧会協会広報部で定めているメディアAD証発行の対象ではなかったため、一般のパスで入場。パビリオンごとに取材許可をもらった。対応はさまざまだったが、概ね記者に対してオープンで、すぐに対応してくれたところがほとんどだった。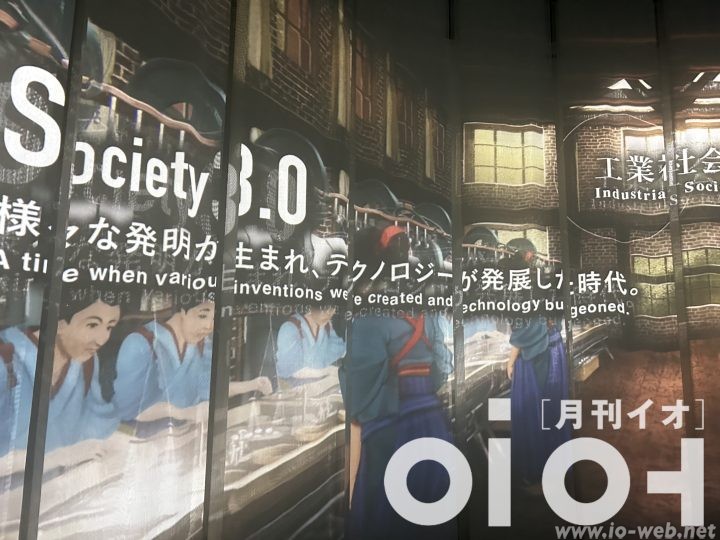
西口ゲートから入場し、まず向かったのは、「未来の都市」パビリオン。ここでは、入り口を抜けると巨大なカーブ状のプロジェクションに地球の誕生から現代社会までをたどり、未来に向けて地球規模の問題が提示されていた。これは期待できると踏んだが、中に進むと「未来都市」をうたったまるで企業商品の展示会のようだった。万博は単なる文化的なイベントではなく、政治・経済的な構造と深く結びついていることを再認識しながら、館を出た。
つづいてハンガリー館。落ち着きのある空間で大人向けなようす。民俗音楽の生演奏は、異文化体験に加え、心落ち着くヒーリング効果を期待できる。本誌でも紹介したがコモンズ-D(コモンズ館とは、複数の国・地域が共同利用するパビリオン)では、ブルキナファソのブースが一押し。現地スタッフに導かれながら、伝統打楽器のジャンベやバラフォンを叩くのは、能動的な文化体験になるだろう。ちなみに、同コモンズ内のパレスチナ館は何やら外国の要人とみられる人々が訪れており、入場制限がかけられていたため断念した。
シンガポール館。それぞれの夢を台上に書くと、文字が飛んでいき、その言葉から「未来都市」が出てくるという演出は子どもから大人まで楽しめるだろう。スタッフは「シンガポールは都市と自然が調和した世界を目指している。みなさんの夢を持って豊かな社会につながる」と話した。
本誌でも触れたアルジェリア館で満足感を得たのち、セネガル館に向かうと、展示物がすべて英語で書かれており圧倒された。玄人向けではあるが、現地スタッフと日本人スタッフがいるため、声をかけてみるといいだろう。
個人的ベストは、オーストラリア館。先住民族のアボリジニが大事にしてきた陸・空・海の大自然を圧倒的な映像技術で堪能できる。アボリジニは「世界最古の天文学者」だとスタッフが紹介してくれた。アボリジニは、天の川の暗黒星雲(エミューの星座)を観察し、エミューの産卵時期を予測してきた。プロジェクションで天空を模して映し出されるエミューなどを観た後、私は自然の壮大さを感じずにはいられなかった。その後、インドネシア館に赴いたが、オーストラリア館の後だったので自然の映像美に感じることが少なかった。
ルクセンブルク館はスマホアプリを独自で作り、訪れた後でも館内の展示を観られたり、映像で等身大の国民の語りを聴けたり、ネットの上に寝転がりルクセンブルクの町並みなどを眺めたり、最後に展示ブースを出るとレストランのブースが待ち構えていたりと、国の魅力を惜しみなくアピールしていた。
そこで、朝鮮学校教員の言葉がふと頭をよぎった。「朝鮮民主主義人民共和国の出展はなかったが、総聯が責任を持ち、朝鮮パビリオンを設置できたのなら、朝鮮と私たち在日朝鮮人について広く世界に知らせることができたのではないか」―そのような趣旨の話だった。朝鮮はこれまでに2010年の上海万博、2015年のミラノ万博で出展していた。
日本でより朝鮮を身近に感じてもらい、私たちの魅力を伝えるには、一つの手段として有効なのではと確かに思った。
また、日本市民でさえ、在日コリアンを知らない人がいることを今回、痛感させられたため(それ自体は歴史教育の失敗だと思うが)、自らをアピールする意義を改めて感じずにはいられなかった。先のシンガポール館前でこんな経験をした。取材許可をもらおうと、日本人スタッフに「メディアの者なんですけど…」と名刺を渡した私。すると、スタッフが「韓国のメディアですか?」と聞いてきたので、「いいえ、主に在日コリアンを対象にしたメディアです」とはっきりと答えると、「わかりました」と了解した。そして、数分後、責任者とみられる人が来た時、そのスタッフは「こちら韓国のメディアの方ですが」と紹介したの だった…。
あとは、モザンビーク、クウェート、オランダ館とめぐり、最後はカラッカラに乾いた喉に、チェコ館のキンキンに冷えたピルスナーウルケルを流し込んだ。
大阪万博をめぐる問題は山積しているが、総じて、この1日だけで、これまで訪れたことのない国々の人と文化に直接触れられる経験は、ほかに代えがたいものだと実感した。本誌8月号で協力いただいた南大阪朝鮮初級学校校長と明戸隆浩さん(大阪公立大学大学院准教授)が共通して言うように、訪れた子どもたちにとって「世界への扉」を開くきっかけに(校長)、「世界」との出会い(明戸さん)になることは間違いないだろう。(哲)










