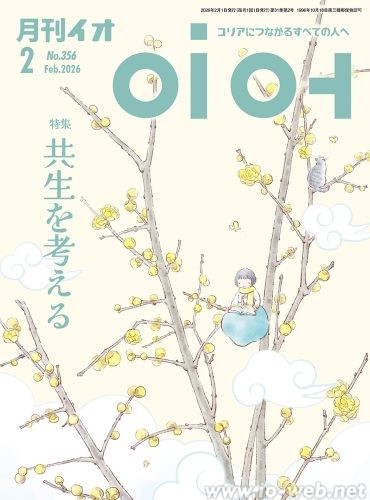雑誌の未来
広告

写真はイメージです
数日前、都内のS支部委員長からありがたい電話をいただいた。本誌が出版した『18人が語る 私とコリアン』の販売代金を振り込みたいので、振込先を教えてほしいとのこと。「お金には足がついてるから、早く振りこまないとなくなっちゃう」と笑う。
昨年9月のことだ。とある集会で私が本の販売に苦戦していたとき、10冊を引き受けてくれたのがS委員長だった。「日本の人たちの集まりで売ってみるから、預かるよ」との言葉に甘え、そこから3ヵ月。年内に売り切ってくれたことに胸が熱くなった。
3週間前には、ある会でお会いしたK支部委員長が、別れ際に「今から1月号のイオを配ります」とおっしゃったので、「何部ですか」と聞くと75部も配っているという。お一人で75部!簡単なことではない。
私たち編集部員は雑誌や本を作っているが、本を売ってくれる人がいないと、この仕事は成り立たない。作ることと同じくらい、届けること=売ることは大切だと、現場にいる方々のお仕事を聞いて再認識する。
今年7月1日に創刊30周年を迎えるイオ。
30年という月日について感慨を覚えると同時に雑誌メディアの未来、同胞メディアの未来についても考える。
日本の新聞記者や雑誌の編集者、フリーライターさんと話していると、皆さん活字の可能性についての話は弾みつつ、部数が広がらないことへの不安を必ず口にする。
一方、日本やお隣の韓国を見ると、ユニークな書店は増えていて、活字文化はすたれていないと思う。しかし部数減は出版業界では切実な課題だ。
部数やサイトのアクセス数は、そのメディアが世に求められているか、読まれているかをはかるバロメーター、なにより一定の部数を確保しなければ、安定した経営ができない。
最近読んだ『持続可能なメディア』(下山進著、朝日新聞出版、2025年)には、苦戦しつつ確実に読者を獲得している雑誌、新聞社、テレビの事例が載っていた。週刊プレジデントは日本で唯一、電子版を成功させたメディアで、分野を特化した特集や企画もので読者をつかんでいる。
北國新聞は石川県の新聞だが、金沢の伝統文化の記事を一面に載せるなど、金沢文化の掘り下げに力を入れている。新聞全体が20年で半分近く部数を落としているなか、同紙は2013年のピーク時から、部数が9%しか落ちていないという。
秋田魁新報は秋田県の出生率や女性のUターン率がなぜ低いかを独自調査。秋田県における女性の生きがたさを他の自治体と比較して調べ、秋田県における課題を浮き彫りにした。独自の報道で読者をつかむことは、メディアの生き残り策として間違いないだろう。
本屋も頑張っている。
兵庫県明石市の「ライツ社」は2016年に生まれた小さな出版社だが、この会社が運営している「明るい出版業界話」には、出版業界の暗い話は出ていない(笑)。ある本屋の二代目は、脱サラした後、書店経営を模索するなか、100人に話を聞いた。そこから生まれたコンセプトは、「本を読む生活に寄り添う」ことの大切さ。「ブックライフ」という考え方を打ち出し、ユニークな本棚やブックトークを企画した話にも心温まる。
創刊当時、30、40代をターゲット世代にした雑誌として始まったイオ。創刊号の特集は、30、40代を大きく写真で紹介した特集だった。一般の同胞を大きく切り取り、ズームアップして紹介した編集が当時としては新しく、新鮮に感じた記憶がある。同胞コミュニティから疎遠になる世代に届けたいとの作り手の思いが、誌面から伝わってくる。
創刊された1996年当時は、パソコンやスマートフォンも普及されておらず、紙媒体はまだ元気で雑誌もたくさんあった。つまり「雑誌」というメディアが新しかったのだ。
30周年という年月は、一つの世代がなくなり、新しい世代が生まれたくらい月日が流れたことになる。
創刊30年後の「今」、求められているメディアは何だろうと考え続けるが、はっきりとした答えは見つからない。
雑誌メディア≒紙媒体は数は減っているものの、今維持している部数こそ、同胞社会の力であり可能性だ。絶対に読んでほしい、手にとってほしいターゲット層に向けて、イオをどう変えていくか。メディアとしてどういう形に進化させていくか。
まずは、「30年」という地点で見える景色をしっかり捉えることが、出版物の持続可能性を考える第一歩だと感じている。(瑛)