沈壽官さんの映画と取材の思い出
広告

11月9日、板橋区立文化会館で行われた映画上映会に行ってきた。
上映されたのは「ちゃわんやのはなし―四百年の旅人―」(監督:松倉大夏、2024年公開)。昨年、第24回「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」の文化貢献部門奨励賞を受賞した作品だ。
上映会を主催したのは日本の人たちによる「東京朝鮮第三初級学校とともに歩む会」で東京第3初級の学区の総聯支部女性同盟が共催した。
今から約420年前、豊臣秀吉の2度にわたる朝鮮侵略の際に日本に連れてこられた朝鮮の陶工たちの末裔の日々をつづったドキュメンタリーだ。
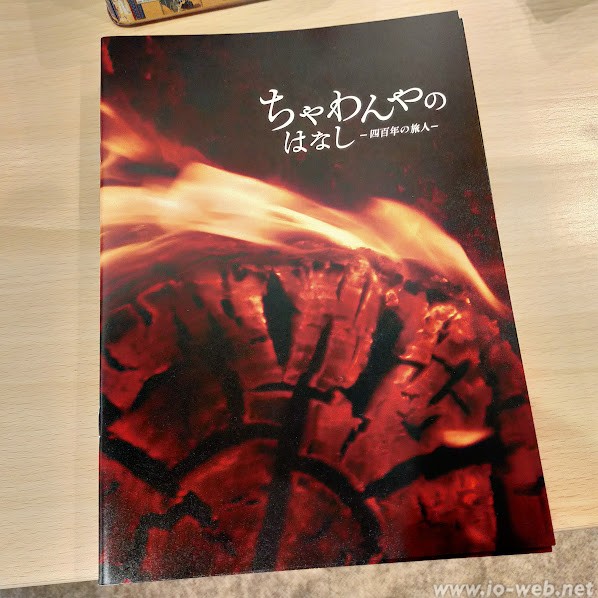
会場で売られていた映画のパンフレット
映画には薩摩焼、上野焼、萩焼の陶工たちが出てくるが、物語で圧倒的に多くを占めるのが薩摩焼の15代・沈壽官さんだ。
沈壽官さんの日常生活や陶器制作の様子などが映し出される。興味深かったのが韓国での修業時代の話や父親である14代との関係性。そして民族について考える姿だ。
なぜこの映画を観に行ったのかというと、私は2014年10月に鹿児島まで行き沈壽官さんを取材したからだ。記事は2014年11月号の月刊イオに掲載した。
家業を継ぐことの葛藤やその後の苦労、伝統を守っていくことの意味、陶芸への思い、「沈壽官」という名を継ぐ決意、朝鮮半島へのまなざしなどを語ってくれた。
沈壽官さんはこちらの質問に本当に率直に答えてくれた。
記事の中で私の「どのような作品を作っていきたいと思っていますか?」という質問に対する沈壽官さんが語ったことの一部を紹介する。
もう一つの側面は、技術というツールを使って、いったい何を言うのかということです。表現の「現」の部分ですね。21世紀に生きている私たちは、いま様々な事案に囲まれています。戦争や異常気象、親子の問題など、様々な問題のなかで、私がどのようなメッセージを届けるのかが大事だと思います。そういった様々な問題から私が思うメッセージ。簡単に言えば「命」ということです。「命」を伝えたい。生きる喜びを伝えたいですね。そうしたメッセージ性がきちんとあって、なおかつ技術的に高いものがいい作品です。生きるということを、薩摩の先人たちが築き上げたいろんな技術を駆使しながら表現できたらいいなと思っています。
今回の映画には取材した時に見た工房や窯などが映し出されていて懐かしかった。(k)










